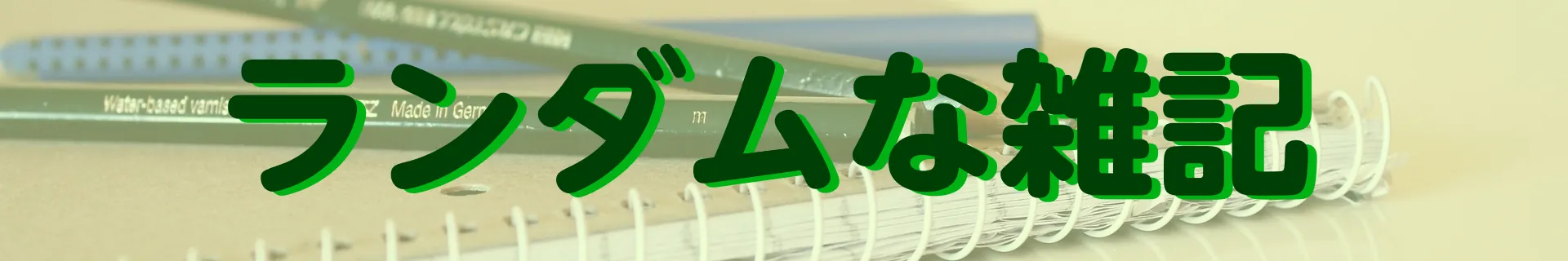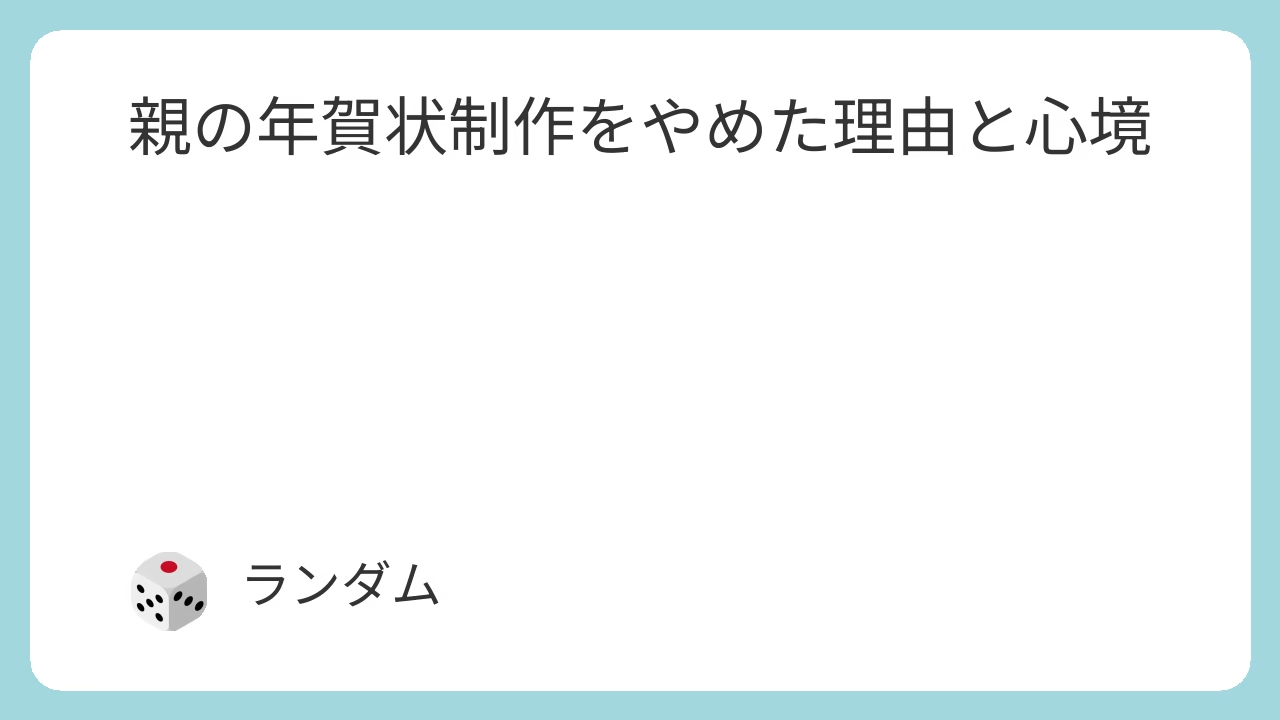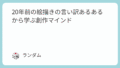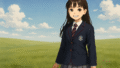はじめに:年賀状、いつまで続けますか?
年末になると「年賀状どうする?」という話題が出てきます。
筆者自身はすでに年賀状を完全にやめた“年賀状否定派”ですが、長年親の年賀状制作を手伝ってきました。
いや、正確には「代行」してきました。
今回は、20年続けた親の年賀状制作サポートをやめた理由と、その裏にある親子の距離感や言葉の意味について考えてみます。
始まりは20年前のプリンター購入から
我が家がPCとプリンターを購入したのは約20年前。
それからは毎年、年賀状をパソコンで作成するようになりました。
筆者が実家を出た後も、年末になると「年賀状作るのを教えて」と呼ばれ、実家へ行って作業するのが恒例に。
「教えて」と言われ続けた20年の実態
「教えて」と言われていたものの、実際はほぼ代行。
親が選ぶのは絵柄やレイアウトだけで、住所録の管理、印刷設定、操作はすべて筆者が担当。
毎年「これで来年は自分でできるね」と思っても、翌年にはまた「教えて」と言われる繰り返し。
2022年、サポート終了宣言
2022年の年末、「来年からはサポートしない」と宣言しました。
その年は最後のサポートとして作業を行い、代替案として郵便局の年賀状作成代行サービスを紹介。
住所録の相談も郵便局へと案内しました。
「教えて」に込められた親の心理とは?
- 本当に覚える気があったけど、覚えられなかった?
- 「教えて=代わりに作って」の暗黙の了解?
- 実家に呼ぶための口実だった可能性も?
言葉の裏にある意図を考えると、親子関係の複雑さが見えてきます。
筆者は徐々に不信感を抱くようになり、親のお金に対するだらしなさもあって、少しずつ距離を取るようになりました。
✉️筆者自身は年賀状否定派
筆者はすでに自分の年賀状は一枚も出していません。
年賀状文化そのものに疑問を感じており、デジタルでの挨拶や必要な連絡は別の手段で済ませています。
✅まとめ:手伝いと代行の境界線を見極める
「教えて」と言われたとき、それは本当に“教える”ことなのか?
親子の距離感や言葉の使い方を見直すきっかけとして、年賀状制作は象徴的な出来事でした。
あなたも、年末の“恒例行事”を見直してみませんか?